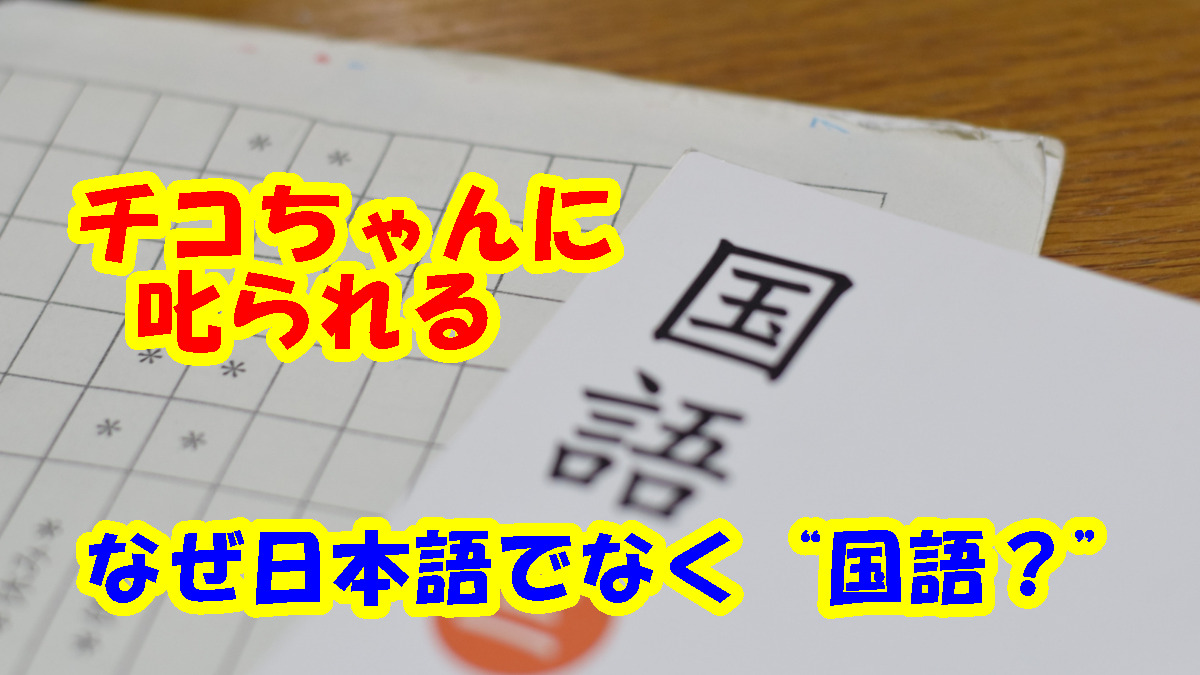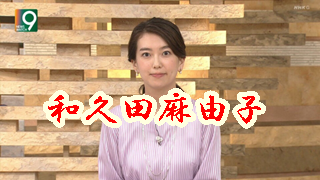チコちゃんに叱られる、過去の問題でなぜ日本語でなく“国語”なの?という問いがチコちゃんから出されました。
その回答は・・・。
国語と言えば、日本語ですよね。でも小中学校での教科書には「日本語」とは書かれていません。
それは「国語」と表示されています。ではなぜ国語なんでしょうか?
ドイツの言葉を学ぶ授業は「ドイツ語」、フランスの言葉を学ぶ時も「フランス語」で英国の言葉は「英国語」とは呼ばず「英語」にしています。
さすがにチコちゃんでこの素朴なギモンを取り上げていました。
“チコちゃんに叱られる”過去の問題。なぜ日本語でなく国語なの?
そこでこの過去の問題にお答えしてくれる先生は、日本女子大学で近代日本語について教えている「清水康行教授」です。
少し思い切った答えですがと前提で答えは「日本を一つにするため」でした。
日本を一つにするため?って日本は一つでないの?とまたまた疑問になってしまいますが、話は徳川幕府の江戸時代に遡ります。
日本史の近代史で学んだと思いますが、徳川幕府が中央集権的な統一国家を形成していたわけではありませんよね。
平和は担保されていましたが、それぞれの大名が支配する独立国のような藩が日本には300近くありました。
日本語は藩の言葉で存在。
いわゆる方言ですよね。今ではTVがあり、スマホがありyoutubeもあり日本国では標準語で皆さん表現しています。
それでも地方に行けば独特のイントネーションがあり関東と関西、そして京都などは今でも独特の言い回しで文化を形成しています。
特に当時の江戸時代では、言葉は場所によってバラバラで共通語は存在していませんでした。
それは、当時の参勤交代のあるお殿様は別として一般庶民は藩の国から出ないで一生を終える人々が主でした。
人々は方言の「おくに言葉」だけで何不自由なく生きていけたのです。
日本語が通じない幕末の維新。
ところが、徳川幕府の幕末になり大政奉還が行われ地方の武士たちも江戸に集まってきました。
その時に先ず困ったのが「互いに何を言っているのかわからない」ことでした。
当時の音声もなく想像もできませんが、あまりにも言葉が違っていたようです。
例えば「ありがとう」と言う言葉を地方では何と言うか?
藩の日本語で「ありがとう」は?
- 東京:ありがとう
- 大坂:おおきに
- 東北:おぎに、むやぐ、もっけだの
- 北陸:きのどくな、あんやと
- 山陰:すまんようにござんす、たえがとう
- 四国:たまるか
- 九州:ちょうじょう、あいがて、おおきん
- 北海道と沖縄:不明
これでは同じ日本人同士でコミュニケーションはできません。
伊藤博文は日本語を単語で表現。
伊藤博文は山口県出身です。
戊辰戦争(明治元年の日本の内戦)で山口県の出身の武士が、山形県の武士たちの取り調べをする際に言葉が通じなかったようです。
そこで、おこなったのが、単語を並べてやり取りをしたそうです。
例えば「問う、年、いかに?」など単語だけを並べてやり取りしたそうです。
東北の山形、中国地方の山口と東と西では言葉が通じません。ですので~候という書き言葉で話をしたとの記録が残っているようです。
明治政府は日本語を“国語”と推奨。
やがて明治にになると、日本は中央政府が全国を治めることになります。
その中で、日本を一つの国としてまとめあげるためには、誰もが共通して理解できる一つの言葉、つまり「標準語」が必要になってきます。
そして標準語を教える授業が「国語」となったのです。
東京帝国大学文学部長を務めた言語学者の上田万年(かずとし)が「国語」と言う言葉使い、
「日本の発展には言葉が必要だ」と説いたことも大きなキッカケになりました。
“チコちゃんに叱られる”過去の問題。日本語の標準語の決定は?
明治政府は、すべての日本人に通じる言葉“標準語”を定める「国語調査委員会」をつくり、全国の言葉を徹底調査を始めました。
そこでの有力候補は2つでした。
日本語対決、京都弁VS江戸弁。
2つの有力候補とは京都で使われていた言葉と、幕府のあった江戸の言葉です。
現在の首都である東京の言葉を推す当時の若手世代の意見と、
長く日本の中心だった古都・京都の言葉を推す年配世代の声も強くありました。
議論は平行線で時間が経過しました。なかなか結論はでません。
そのまま10年以上の歳月がたちました。
京都派の高齢者が亡くなった明治37年に“東京の教養ある人々が使う言葉”を標準語とし、子どもたちに教えることが決定したのです。
京都弁が日本語の標準語になっていたら・・・。
天気予報でも、
あすは関東から西日本にかけてよおぅ晴れます。せやけど、えげつのう朝冷え込みまっさい、きいつけておくれやす。
となりますよね。
今では私たちは標準語に慣れてしまったので京都弁でニュースが流れると不自然と思うかもしれませんが、
当時標準語が京都弁で決まっていたならこのようになっていたのです。
まとめ。
明治37年は西暦1904年です。
今から116年前、1世紀前に“東京の教養ある人々が使う言葉”を日本の標準語として使うことが決まりました。
この「国語」のおかげで、日本全国で同じ言葉を理解できたことは素晴らしいことです。
でも地方の言葉がなくなったわけではありません。
今でも地方の方言は残っていますのでそれはまた文化として残してもらいたい言葉ですね。